▼山の伝承神話【本文のページ】(09)
【とよだ時】(豊田時男)
……………………………………
山旅【ひとり画ッ展】
▼北アルプス・五竜岳は立山の後ろ山
(長文です。拾い読みしてください)
▼五竜岳は立山の後ろ山
【説明本文】
北アルプスの五龍岳(標高2814m)は、
長野と富山の県境になっている後立山連峰の
ほぼ真ん中にある山です。この山の山頂東面
G2と呼ばれる大きな岩峰の崖には、X字形
の割れ目があります。
ふもとの村人は、断崖で冬でも雪が付かな
いような岩壁を「菱(ひし・りょう)」と呼
んでいたそうです。この「菱」には割れ目が
あるため、割り菱と呼んだとか。
菱のまわりに雪が積もると、菱が黒く目立
ちます。またX字の割れ目にも雪が付きはじ
めると、遠くからは「四つ割り菱」の雪形に
なって見えます。
それはまるで当時ここを支配していた武田
信玄の家紋と同じです。そのためご領主さま
に気兼ねしたのか、「御」の字をつけて「御
菱」と呼ぶ者も出てきます。
明治も41年(1908年)の7月、三枝威之
介一行が北方の白馬岳から縦走。登山家とし
て初めてこの山にさしかかりました。しかし
地図には山の名前が載っていません。
地元の案内人に聞くと「ゴリョウ」という
山だとの説明。漢字を聞きましたが分かりま
せん。三枝は「それでは五龍と書いておこう」
とメモします。これが東京で雑誌に発表され
ました。
のち昭和6年5月、お上が発行した五万分
の一の地形図にも「五龍岳」の文字が記載さ
れて、とうとうこれが本名になってしまった
のだそうです。
山名についてはそのほか、信仰の山として
賑わった富山県立山側から見て後にあるので
「後立(ごりう)山」説や、「五鯉鮒山」説
があるそうです。
また、きり立った崖の山は、そのまま呼べ
ばただの崖岳(山)です。ガケ岳がなまって
ガキ岳になり、仏教の影響もあって「餓鬼岳」
の字を当てるようになります。各地にある餓
鬼岳はたいていそんな山です。
ここ五竜岳も崖の目立つ山。江戸時代、村
人は餓鬼岳とも呼んでいたといいます。とこ
ろが、いつのまにか五龍岳と名前が変わり、
お上発行の地図にも記載されるしまつ。
しかし、地元の人はすぐには代わりません。
依然として餓鬼岳と呼びます。お上にとって
それでは困ります。
しかたなく思いついたのが、別の山に餓鬼
岳の名前をつける方法。それが北西・富山県
側にある2128mの峰、餓鬼岳。
そういえば、もとの餓鬼岳(五竜岳)に突
きあげる黒部川の支流・餓鬼谷もその東側直
下を流れていて、一見関係がありそうに思え
ます。うまい場所をみつけたものですね。
ところで、後立山連峰は、北は白馬岳から
鑓(やり)ヶ岳、唐松岳、五竜岳、鹿島槍ヶ
岳から急にカーブ、冷池(つべたいけ)、爺
ヶ岳、岩小屋沢岳に至る稜線は、まるで北斗
七星のひしゃくのような形です。そのアリオ
ス星にあたるのが五龍岳となっています。
この長大な連峰、後立山連峰、いまは長野
・富山県境になっていますが、江戸時代のは
じめまでは信州側では黒部川、立山あたりま
で自分の領地と考えていたといいます。
しかし、富山県側・加賀藩前田家にとって
は、後ろに控える信州松本藩の奇襲が脅威で
す。そこで一方的に後立山連峰から西を立入
禁止にしてしまったのだそうです。
そうなっては山仕事や猟など、松本藩にと
っては打撃です。あわてて抗議しましたが、
なんといっても七万石の身には加賀藩の百万
石はあまりにも大きな差。
結局天保年間(1830〜44)になって、い
まの境界に押し切られてしまったということ
です。さぞや悔しかったことでしょうね。
▼五龍岳【データ】
★【所在地】
・長野県大町市と富山県黒部市宇奈月町旧地
区との境。大糸線神城駅の西8キロ。JR大
糸線神城駅からテレキャビンを利用歩いて8
時間で五龍岳。写真測量による標高点(2814
m)と三等三角点(停止【亡失】)(基準点成
果等閲覧サービスであらわれる)がある。
★【位置】国土地理院「電子国土ポータルWe
bシステム」から検索
・標高点:北緯36度39分30.28秒、東経137度
45分9.58秒
★【地図】
・2万5千分の1地形図「神城(高山)」と「十
字峡(高山)」(2図葉名と重なる)。
▼【参考文献】
・『アルパインガイド27・白馬岳・後立山連
峰』高橋伸行(山と渓谷社)1979年(昭和54)
・『角川日本地名大辞典20・長野県』(角川
書店)1991年(平成3)
・『新日本山岳誌』日本山岳会(ナカニシヤ
出版)2005年(平成17)
・『富山県山名録』橋本廣ほか(桂書房)2001
年(平成13)
・『日本山岳ルーツ大辞典』村石利夫(竹書
房)1997年(平成9)
・『日本山名事典』徳久球雄ほか(三省堂)2004
年(平成4)
・『山の紋章・雪形』田淵行男著(学習研究
社)1981年(昭和56)
…………………………………………
【広告】です。スイマセン
★作者の本をどうぞ(アマゾンから)。
【とよだ時】(旧とよた時)コーナーです。
https://www.amazon.co.jp/stores/author/B004L1SDTE
★下記はCD本です。(作者から発送します)。
天狗・仙人・神仏に出会う山旅。
・00『百名山の伝承と神話』(新)
・01『新・丹沢山ものがたり』
・02『全国の山・天狗ばなし』
・03『山の神々いらすと紀行』
・04『山の神々いらすと紀行・続』
・05『ふるさとの神々事典』
・06『ふるさとの神々事典・続』
・07『野の本・山の本』
・08 ↓こちらもどうぞ(紙書籍版品切れ)
「電子書籍」または「中古書籍」をどうぞ。
▼山と渓谷社刊『日本百霊山』
神仏、精霊、天狗や怪異と出会う山旅。山の愉
快な話
<アマゾン>で。 <楽天ブックス>で。
………………
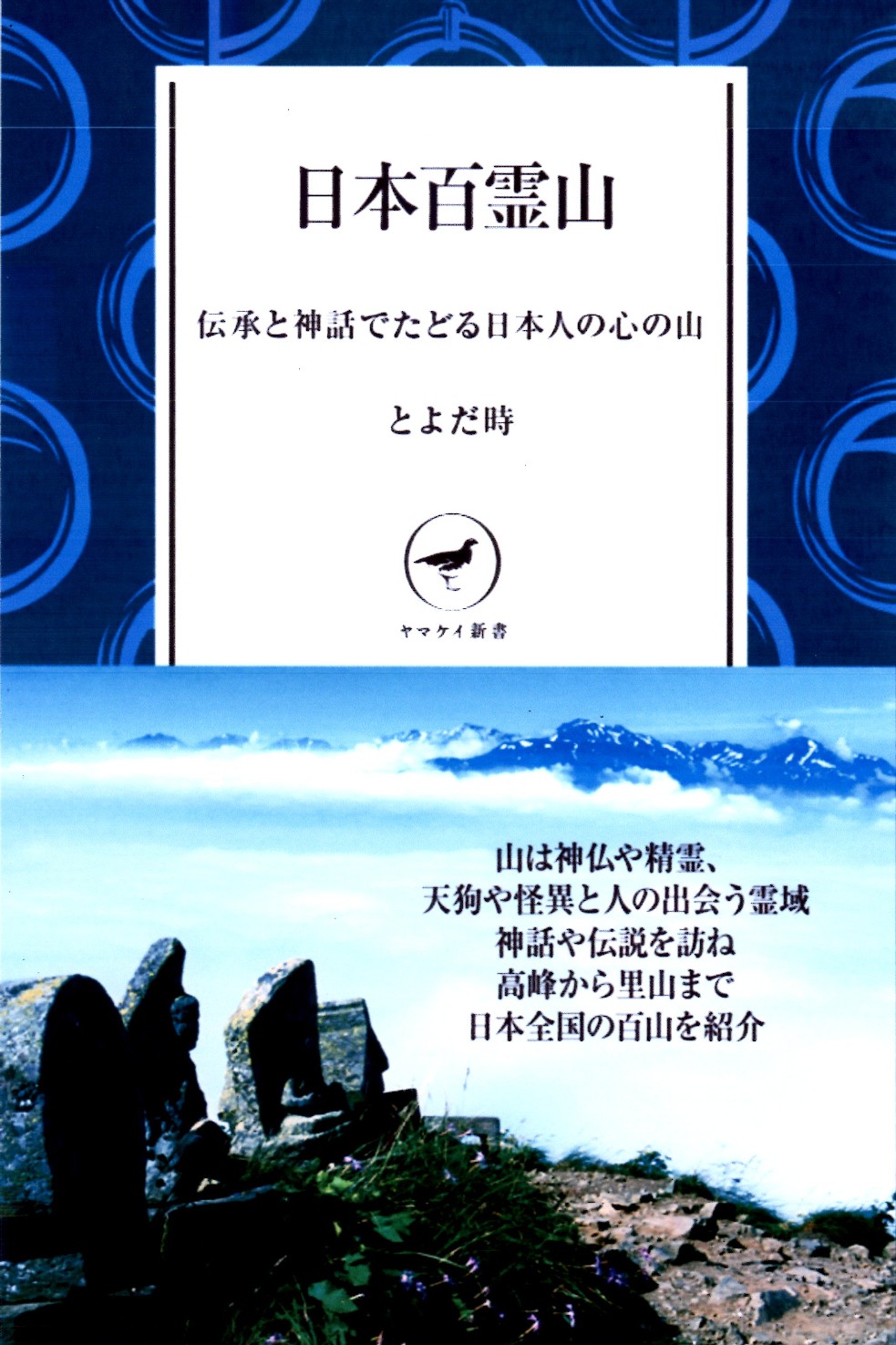
https://toki.moo.jp/cd-mihon/cd-mihon.html
※(CD総合見本)
▼SNSやっています
★Facebook:
https://www.facebook.com/tokitemg
★X(旧ツイッター):
https://x.com/tokitemg……………………
【TOP】ページ「峠と花と地蔵さんと……」へ
……………………………………………………
|