山旅通信【ひとり画ッ展】
『日本百名山』の伝説と神話
(山の神・伝説神話)
【本文のページ】(10)
……………………………………
山旅通信【ひとり画ッ展】1200号
▼『百名山の伝説神話』100番
「屋久島宮之浦岳のはなし」
「宮之浦岳と海幸山幸神話」
(このシーズ・最終回)
(長文です。ご興味ある部分を拾い読みして
ください)
★【本文の目次】
・【宮之浦岳とは】
・【山頂】
・【山頂の祠】
・【益救(やく)神社】
・【祭神】
・【岳参り】
・【女人禁制破り】
・【屋久どんと種子どん伝説】
・【山のオン助伝説】
・【宮之浦岳データ】
・【参考文献】
▼【本文】
★【宮之浦岳とは】
宮之浦岳(1936m)は、屋久スギで名高
い鹿児島県屋久島にある九州の最高峰の山。
ここは雨が多いことで有名で、「1ヶ月に35
日雨が降る」といわれるくらいで、年間降雨
量が、山頂部で8000ミリに達するといいま
す。島の山は標高1500m以上が連なり、そ
れを総称して八重岳と呼んだり、「洋上のア
ルプス」ともいっています。
とくに宮之浦岳、永田岳、黒味岳の3座は、
三岳(みたけ)とか奥岳とも呼んでいます。
これらの山々には小さな祠があり、それぞれ
に一品宝珠(寿)大権現(いっぽんほうじゅ)
という仏教の神をまつっています。宮之浦岳
の山頂は双耳峰で、東峰が1867mの栗生岳
で、西峰に(▼確認のこと??)1934.9mの
一等三角点があります。
山頂は風化した奇岩、奇石多く、ヤクシマ
シャクナゲが生えており、永田岳やまわりの
山々、種子島などなどまさに360度の展望で
す。その直下に笠石と呼ばれる巨岩があって、
その下に祠が鎮座しています。
★【山頂の祠】
この祠こそ、一品宝珠(寿)権現のもので、
北東側山ろくの宮之浦地区にある益救神社
(やくじんじゃ)の奥ノ院だそうです。祠は
安土桃山時代の天正14年(1586)と、その
後に建立されたものといいます。それはまた、
永田岳など島内にある山々にある祠などをま
とめる奥ノ院でもあるそうです。ここの里宮、
宮之浦地区益救神社は、宮之浦地区や宮之浦
岳の名前の元になっているといいます。
★【益救(やく)神社】
屋久島は大昔、益救(やく)と呼ばれてい
たそうで、その海沿いの入り江に益救神社が
あり、このお宮から宮之浦の名が生まれたと
いうのです。山頂笠石の下にまつられている
一品宝珠(寿)権現は先述のように仏教の神
で、神道での呼び方は、天津日高彦火々出見
命(あまつひこひこほほでみのみこと)とい
う神になります。
これは神仏習合のあらわし方で、火火出見
命は一品宝珠権現の化身ということになって
います。さてこの益救神社には、彦火火出見
命のほかに、山と海の7柱の神がまつられて
います。この彦火火出見命がまた、別名山幸
彦なのだといいますからメッチャややこし
い。あの「海幸山幸」神話に登場する「山幸
彦」です。そして、初代天皇といわれている
神武天皇の父だというから気が遠くなりま
す。
★【山幸彦】
この山幸彦は、『古事記』(上つ巻)では、
「…次に、生まれる子の御名は、火遠理命(ほ
をりのみこと)。亦(また)の名は、天津日
高日子穂々手見の命(あまつひこひこほほで
みのみこと)……」とあり、山佐知?古(や
まさちびこ)と書かれ、火遠理命または天津
日高日子穂々手見の命ともいっています。
また『日本書紀』(神代下)には、「彦火火
出見尊(ひこほほでみのみこと)、自(おの)
づからに山幸(やまさち)有(ま)します」
とあります。
この山幸彦が兄から借りた釣り針を鯛にと
られ、悲嘆にくれていたとき、潮流の神の神
である塩椎神(しおつち)に教えられ、島の
ワタツミの宮殿に行きました。そして竜女の
化身である豊玉姫命(とよたまひめ)と巡り
会い結婚することになります。
そしてとなりの島の種子島で、一子をもう
けるというストーリーです。その子の名は『日
本書紀』では、彦波瀲武??草葺不合尊(ひ
こなぎさたけうがやふきあえずのみこと)と
表記。亦の名、『古事記』の表記では、天津
日高日子波限建鵜葺草葺不合命(あまつひこ
ひこなぎさたけうかやふきあへずのみこと)
といいます。亦の名、亦の名つづきで、シッ
チャカメッチャカで恐縮です……。
★【岳参り】
さて、この屋久島には毎年春と秋に御岳に
登る「岳参り」という民俗行事があります。
「岳参り」は、五穀豊穣・国家安穏・延命息
災を祈願しに、この奥宮に登ります。春の岳
参りは日帰りで登り、秋は大願成就のため2
泊3日で登ったといいます。ここもかつては
女人禁制でした。
★【女人禁制破り】
ところが、この女人禁制を無視して、妻を
連れて登った島の役人がいたと江戸時代後期
の薩摩藩の地誌『三国名勝図会』に記載があ
ります。同誌の馭謨郡(ごむぐん)の項に、
「正徳(江戸中期)の比(ころ)、宰官(領
主)伊集院善太夫忠代」という人の話が載っ
ています。
その領主が、わが領地では「山ノ神といえ
ども我が配下である。自分の山に登って何が
悪い!」とばかり、禁制を無視、妻を連れだ
って登りました。しばらく登って行きました
が、途中で天気が急変。雨風が激しくなって
きました。
とうとう進退きわまり、ついに山腹で野宿
する羽目となり、ついに山に登るのをあきら
めて引き返したとあります。そうです。そこ
が宮之浦岳頂上から少し下った平らな原っ
ぱ、「善大夫(ぜんだいふ)泊」という場所
だそうです。こんな禁制を破って神の怒りに
ふれた話は、東北の飯豊山や北アルプスの立
山にもあります。
★【屋久どんと種子どん伝説】
さてお話し変わって、屋久島と種子島の民
話に大男の「屋久どんと種子どん」という話
があります。昔、屋久島の高山に「屋久どん」
という大男がすんでいて、奥山の高山でゆっ
くり昼寝を楽しんでいました。となりの種子
島にも「種子どん」という巨人がすんでいま
した。ところが種子島には200m以上の山
はなく、人里も近く、うっとうしくて昼寝も
ままなりません。
種子どんは、山あり谷ある屋久島がうらや
ましくてしょうがありません。そこで種子ど
んは、屋久島を種子島にくっつけちゃおうと
思い立ちました。屋久どんが屋久島の宮之浦
岳で、昼寝をしているすきを見て、種子どん
は太く丈夫な縄で屋久島をしばって持ち上げ
ようとしました。その時、タヌキ寝入りをし
て様子を見ていた屋久どんが、山が裂けるよ
うな大きなおならをしました。
びっくりした種子どんが振り向いたとた
ん、縄が切れて屋久島はもとのところにドシ
ャーンと落ちました。うす目を開けて見てい
た屋久どんは、「わっはっはっはっ」と大笑
い。「この島がそんなに欲しいなら、屋久島
の岩をひとかけらやってやるわい」といいな
がら、永田岳(そのころ屋久島で最高峰だっ
た)の頂上を少しもぎ取って投げました。そ
れがいま種子島の平山地区の田んぼにある、
大岩とか天狗岩とかいう大岩。岩は高さ30
mもあり、縄でしばったような2筋のくびれ
跡も残っているのも不思議です。
★【山のオン助伝説】
そのほか、屋久島の山には不思議なことが
多い。10月になれば、山と山との間に太鼓
の音がドン、ドン、ドンと、ゆっくり聞こえ、
それが夜明けになると、ドンドンドンドンド
ン……と早く聞こえてくるといわれます。こ
れは天狗の「山のオン助」が暴れている音だ
そうです。
神無月(10月)になり、神さまがみんな
出雲に出かけます。このあたりの神が留守に
なるのをいいことに、山の天狗が暴れるのだ
というのです。「山のオン助」は、宮之浦岳
の大天狗、一品宝珠(寿)権現(いっぽんほ
うじゅ)の眷属の小天狗ではないかと地元の
人は見ています。
そうだとすれば、宮之浦岳の山の神は一品
宝珠権現であり、また小天狗などを眷属に持
ってこのあたりの山々を守っている大天狗で
もあったようです。
▼宮之浦岳【データ】
★【所在地】
・鹿児島県熊毛郡屋久島町。宮之浦港からタ
クシー、淀川入り口下車、歩いて50分で淀川
小屋(泊)。淀川小屋から歩いて6時間で宮
之浦岳。一等三角点(1934.92m)と、写真
測量による標高点(1936m)がある。
★【位置】国土地理院「電子国土ポータルWe
bシステム」から
・標高点:北緯30度20分9.42秒、東経130
度30分15.35秒
・三角点:北緯30度20分10.05秒、東経130
度30分15秒
★【地図】
・2万5千分1地形図名:宮之浦岳
▼【参考文献】
・『角川日本地名大辞典46・鹿児島県』(角
川書店)1991年(平成3)
・『神々の系図』川口謙二(東京美術)1981
年(昭和56)
・『古事記』:新潮日本古典集成・27『古事記』
校注・西宮一民(新潮社版)2005年(平成17)
・『コンサイス日本地名事典』三省堂編修所
(三省堂)1987年(昭和62)
・『三国名勝図会』: 60巻 17(巻之49-51)五
代秀尭, 橋口兼柄
共編(出版者・山本盛秀)
1905年(明治38)
・『新日本山岳誌』日本山岳会(ナカニシヤ
出版)2005年(平成17)
・『図聚天狗列伝・西日本』知切光歳著(三
樹書房)1977年(昭和52)
・『天狗の研究』知切光歳(大陸書房)1975
年(昭和50)
・『日本山岳ルーツ大辞典』村石利夫(竹書
房)1997年(平成9)
・『日本三百名山』毎日新聞社編(毎日新聞
社)1997年(平成9)
・『日本山名事典』徳久球雄ほか(三省堂)2004
年(平成16)
・岩波文庫『日本書紀(一)』校注・坂本太
郎ほか(岩波書店)1995年(平成7)
・『日本の民話25』(屋久島篇)下野敏見編
(未来社)1974年(昭和49)
・『日本歴史地名大系47・鹿児島県の地名』
(平凡社)1998年(平成10)
(このシリーズ・最終回)。その他の山はこち
らです。
https://toki.moo.jp/gaten/index.html
…………………………………………
ちょっと【広告】です。スイマセン
★作者の本をどうぞ(アマゾンから)
【とよだ時】(旧とよた時)コーナーです。
https://www.amazon.co.jp/stores/author/B004L1SDTE
…………………………
★グッズあります。SUZURI社で販売しています。
https://suzuri.jp/toki-suzuri
…………………………………………
ちょっと【広告】です。スイマセン
★作者の本をどうぞ(アマゾンから)
【とよだ時】(旧とよた時)コーナーです。
https://www.amazon.co.jp/stores/author/B004L1SDTE
…………………………
★グッズあります。SUZURI社で販売しています。
https://suzuri.jp/toki-suzuri
…………………………
★下記はCD本です。(作者から発送します)。
山の妖怪神仏に出会う山旅。
・00『百名山の伝承と神話』(新)
・01『新・丹沢山ものがたり』
・02『全国の山・天狗ばなし』
・03『改訂・山の神々いらすと紀行』
・04『改訂・ふるさとの神々事典』
・05 ↓こちらもどうぞ(紙書籍版品切れ)
「電子書籍」または「中古書籍」をどうぞ。
▼山と渓谷社刊『日本百霊山』(電子書籍)
神仏、精霊、天狗や怪異と出会う山旅。山の愉
快な話。神話伝説姉妹版
<アマゾン>で。 <楽天ブックス>で。
………………
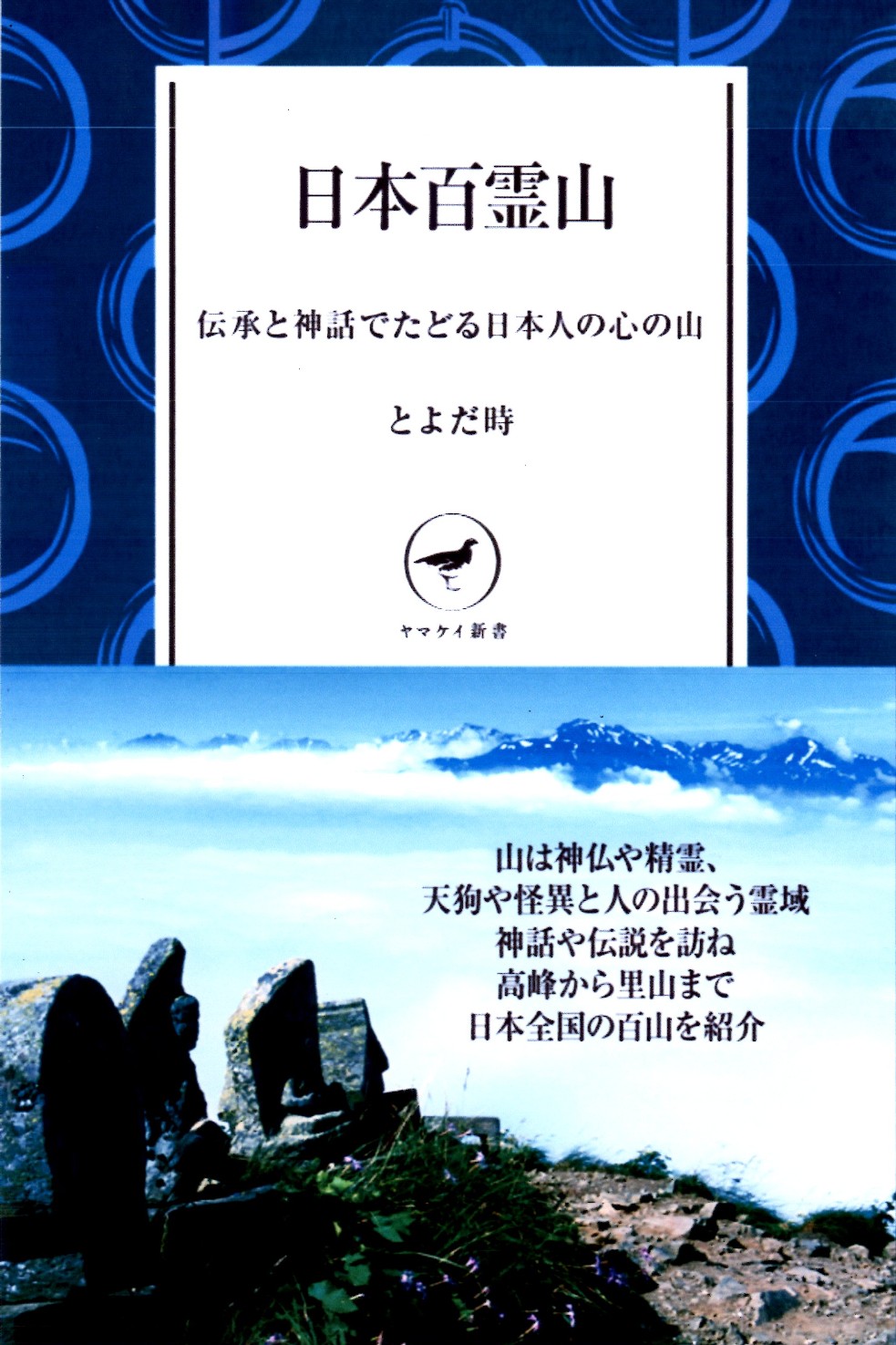
★その他CD本。
https://toki.moo.jp/cd-mihon/cd-mihon.html
▼SNSやっています
★Facebook:
https://www.facebook.com/tokitemg
★X(旧ツイッター):
https://x.com/tokitemg
……………………
【とよだ
時】山と田園の民俗伝承探査・漫画家
from
20/10/2000



|