『日本百名山の伝説・神話』
本文のページ(01)
【とよだ時】(豊田時男)
……………………………………
▼北海道・利尻岳(山)

【本文】
北海道利尻島の利尻山(1721m)は日本
最北の山。利尻岳とも書かれ、島そのものが
ひとつの山になっていて、美しい姿から利尻
富士とも呼ばれています。深田久弥の『日本
百名山』に出てくるトップの山なのはおなじ
みです。ここには不思議なことに熊やマムシ
などのヘビ類がいないという。
深田久弥は『日本百名山』の中で、かつて
利尻島南東方向対岸の北海道天塩(てしお)
町で山火事があった時、火事現場から逃れて
きたのか熊が泳いで渡ってきて、すみついた
ことがあったという。しかし、いつの間にか
いなくなっていた。たぶんまた古巣へ泳ぎ帰
ったのだろう、というようなことを書いてい
ます。
山名はアイヌ語の「リ・シリ」の音訳「高
い島山」という意味で、となりの低い島山「礼
文」に対するもの。この山は、島の中央に山
頂を突き上げ、北峰(1719m)、本峰、南峰
(1721m)の3つのピークを持っています。
しかし北峰から先は崩落が激しく登山禁止に
なっています。
北峰に利尻郡利尻富士町鴛泊(おしどまり)
地区にある利尻山神社の奥社の祠がありま
す。利尻山北ろくには鴛泊ポン山(444m)、
南麓に鬼脇(おにわき)ポン山(410m)、
仙法志(せんほうし)ポン山(320m)など
という一風変わった名前の小さな寄生火山も
あります。また北に直径250mの姫沼、南麓
の沼浦(ぬまうら)には直径400mのオタド
マリ沼、三日月沼があり、山の風景に趣をそ
えて利尻富士観望の地となっています。
この山は古くから高くそびえた美しい姿
で、航海や漁場の目印にされ、海の安全を願
う人々から崇められたという。しかし姿に似
合わずこの山の気象は厳しく、天気が晴れて
山の姿があらわすのは、1年のうち100日も
ないということです。また利尻山に吹き込む
風は「北海の荒法師」とも呼ばれるほど烈し
いという。ここ利尻島には長くアイヌの人た
ちが住んでいました。
ここに初めて和人が入ってきたのは1706
年(宝永3)。能登の人、村山伝兵衛が松前
藩からソウヤ場所の漁場請負人を命じられ
て、住みはじめたのが開発の先駆けだそうで
す。1787年(天明7)8月にはフランスの
探検家、ラ・ペルーズという人が、サハリン
島から南下した時、宗谷海峡でこの山を見て、
館長のラングルにちなんでラングル峰と名づ
けたという。
登山の古い記録としては、江戸時代後期の
1789年(寛政10)、武藤勘蔵の『蝦夷日記』
のバッカイベツからソウヤへの7月7日の見
聞記があり、それによると、最上徳内(もが
みとくない・江戸時代中後期の探検家であり
江戸幕府普請役)が記されていてこれが最初
らしい。江戸時代後期の1808年(文化5)
ロシア武装船の来襲のときには、幕府から出
兵を命じられた会津藩士が水腫病におかか
り、多数死亡した事件もあったという。
山頂北峰にある神社の里宮、鴛泊の利尻山
神社(祭神は大山祇神(おおやまつみのかみ)、
大綿津見神(おおわたつみのかみ)、豊受姫神
(とようけひめのかみ)を合祀)は1824年(文
政7)に建立した神社だという。そののち、
山頂に奥社の小祠をまつりました。山頂の三
角点(点の名称「利尻絶頂」)は、1912年(大
正元)5月に陸地測量部の技師井口貫一によ
って選点されたものという。
さらに1871年(明治4)日本政府の招き
で開拓使顧問として来日した、アメリカの農
政家、ケプロンが書いた「ケプロン報文」(来
曼北海道記事)には「バツカイ(稚内市の地
名)近傍ノ海浜通リ数英里ノ間、殆ド円錐状
ニシテ、四側平等ナル利尻山ノ美景ヲ眺望シ
ツヽ経過セリ」と利尻山を見ながら航海して
いたことが記されています。利尻山の登山道
を開いたのは修験者天野磯次郎という人物。
1890年(明治23)ころ、鴛泊(おしどまり)
からの登山道をつくったのが最初だという。
明治後期になると、植物学者牧野富太郎が植
物採集のためこの山を訪れています。
また「♪山は白銀、朝日を浴びて……」の
詩でおなじみの『スキーの歌』の作詞家、時
雨音羽がこの利尻出身。彼は利尻山について
「山は世界に山ほどあれど海の銘山これひと
つ」と詠んでいます。島の沓形岬公園には彼
の「ドンとドンとドンと波のり越えて一挺二
挺三挺八挺櫓で飛ばしゃ……」という『出船
の港』の歌碑もあります。
利尻山は、古くは利後(りいしり)山と呼
ばれたという。この山について民俗学者、吉
田東伍は、「(現代文で書くと)島の中央に屹
立する休火山にして、洋名をランタンという。
壮麗なる円錐形をなして裾を四方に延ばし、
遠くこれを望めば、さながら富岳のようであ
る。よって北見富士の名称がある。山ろくは
おおむね樹林をもって覆われ、四合目以上は
全く火山質の石礫(せきれき)をもって覆わ
れている」というような紀行文を残していま
す(『日本山岳ルーツ大辞典』)。
ここは高山植物でも名高いところでもあり
ます。緯度が高いために本州では標高2000
mあたりに生息する高山植物が、利尻島では
平地に平気な顔をして?生えています。ここ
の固有種のリシリヒナゲシ、ボタンキンバイ、
リシリオウギ、リシリトウウチソウなど、利
尻の名を冠した種も多く、南斜面に群生する
チシマザクラは、1968年(昭和43)道天然
記念物に指定されました。
また3合目、姫沼分岐近くにわき出る寒露
泉は1985年(昭和60)の「日本名水100選」
(環境庁)のなかで一番北の名水になってい
ます。この名水は、サケのふ化事業にも利用
されています。深田久弥選定「日本百名山」
第1番選定。岩崎元郎選定「新日本百名山」
第2番選定。田中澄江選定「花の百名山」(1981
年)第12番選定。田中澄江選定「新・花の
百名山」(1995年)第11 番選定。
▼利尻岳【データ】
【所在地】
・北海道利尻郡利尻町と利尻富士町との境。
JR宗谷本線稚内下車、稚内港から船で2時
間で鴛泊(おしどまり)からタクシーで利尻
北麓野営場、さらに歩いて6時間で利尻岳(利
尻山)北峰。2等三角点亡失(1718.7m・2011
年10月31日)と利尻山神社奥宮がある。
【位置】
・北峰2等三角点(亡失):北緯45度10分
49.64秒、東経141度14分28.83秒
・南峰標高点:北緯45度10分42.57秒、東
経141度14分31.67秒
【地図】
・2万5千分1地形図名:鴛泊
▼【参考文献】
・『角川日本地名大辞典1・北海道(上)』(角
川書店)
・『新日本山岳誌』日本山岳会(ナカニシヤ
出版)2005年(平成17)
・『日本山岳ルーツ大辞典』村石利夫(竹書
房)1997年(平成9)
・『日本三百名山』毎日新聞社編(毎日新聞
社)1997年(平成9)
・『日本山名事典』徳久球雄ほか(三省堂)2004
年(平成16)
・『日本百名山』(新潮文庫)深田久弥(新潮
社)1979年(昭和54)
・『日本歴史地名大系1・北海道の地名』高
倉新一郎ほか(平凡社)
▼こんな話をCDにまとめてあります。
【山のCD本・見本】
……………………………………
【広告】ご希望の方にお譲りしています
▼【おもしろ山と田園の本・見本】
・01『新・丹沢山ものがたり』
・02『伝承と神話の百名山』
・03『全国の山・天狗ばなし』
・04『山の神々いらすと紀行』
・05『続・山の神々いらすと紀行』
・06『ふるさとの神々何でも事典』
・07『続・ふるさとの神々事典』
・08『家庭行事なんでも事典』
・09『健康野菜と果物』
・10『ひとの一生なんでも事典』
・11『ふるさと祭事記(歳時記)』
・12『野の本・山の本』
…………………………
▼山と渓谷社刊『日本百霊山』(紙書籍・電子書籍)
神仏、精霊、天狗や怪異と出会う山旅。山の知識を
もう一つアップ。
★ヤマケイ『日本百霊山』ホームページ
https://www.yamakei.co.jp/products/2816120561.html
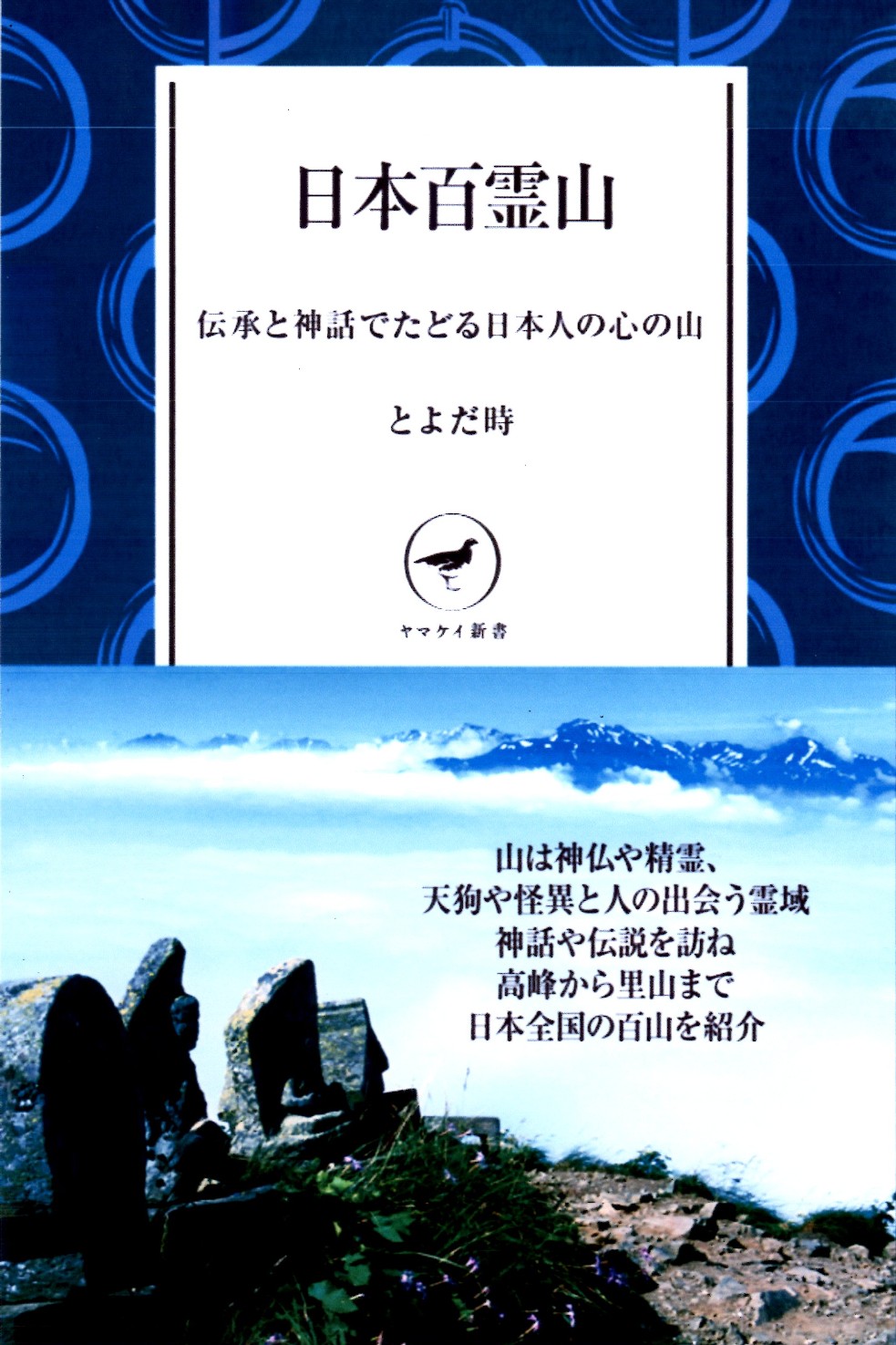
山の伝説伝承神話が満載の本
……………………………………
【TOP】ページ「峠と花と地蔵さんと……」へ
………………………………………………………………
|