山旅通信【ひとり画ッ展】
『日本百名山』の伝説と神話
(山の神・伝説神話)
【本文のページ】(06)
……………………………………
山旅通信【ひとり画ッ展】1196号
▼日本百名山(96番)祖母山のはなし
「嫗岳大明神の蛇体神婚譚と一角竜駒」
(長文です。ご興味ある部分を拾
い読みしてください)
★【目次】
・【祖母山とは】
・【山名】
・【神武天皇の祖母説】
・【古名添山説】
・【山頂の二つの石祠】
・【支配権争い】
・【緒方三郎惟栄伝説】
・【竜駒伝説】
・【登山史】
・【データ】
・【参考文献】
▼【本文】
★【祖母山とは】
宮崎県高千穂町と大分県豊後大野市(旧緒
方町)、竹田市にまたがる祖母山(そぼさん)は、
標高1756m。深い原生林に覆われ、1965年
(昭和40)に祖母傾国定公園に指定され、特別
天然記念物のカモシカも生息。鉱物も銅、錫、
亜鉛などを産し、古くから周辺に土呂久、尾平
(おぴら)、見立、九折(つづら)などの採鉱所が
栄えましたが、いまは廃墟となっています。
祖母山の山名は、山頂にある祠の祭神の豊
玉姫命(とよたまひめのみこと)が、神武天皇の
祖母に当たることからきているという説と、『日本
書紀』に出てくる添山(そほり)説の2つががあり
ます。
山頂からの展望は360度。北東には由布岳
や九重連峰が、西には阿蘇の山々、その後方に
は雲仙岳が、南には日向の山々が、また霧島連
山も一望できます。この山は高山植物も豊かで、
山名がつくウバガダケニンジンやキレンゲショウ
マ、それに初夏にはツクシアケボノツツジ、ツクシ
シャクナゲなどが咲きます。
★【山名】
別名は、姥ヶ岳(うばがだけ)、嫗ヶ岳(嫗嶽・う
ばがだけ)、鵜羽ヶ岳(うばがだけ)、添利山(そ
ほりやま)などというそうです。古くは「ウバガタ
ケ」「オバガタケ」とも呼ばれており、祖母山(そぼ
さん)と呼ばれるようになったのは比較的新しい
らしい。この山が「ウバガタケ」から「祖母山」と、
『古事記』や『日本書紀』などにでてくる「神話の
山」になったのは、国学の隆盛とともに各地に尊
皇思想が広がった、江戸後期から幕末にかけて
のことだといいます。
さて祖母山の山名は、(1:山頂にある祠の祭
神の豊玉姫命(とよたまひめのみこと)が、神武
天皇の祖母に当たることからきているという説と、
(2:『日本書紀』に出てくる添山(そほり)説の2つ
ががあります。
★【神武天皇の祖母説】
そのなかの(1:の神武天皇の祖母説につい
て、江戸時代後期1803年(享和3)の『豊後国
志』(いまの大分県の地誌)は、「嫗岳(祖母山)」
の項で、「又(の)名祖母、蓋(けだし)山配祀豊
玉姫(とよたまひめ)命、以(て)神武帝為皇祖母
故也」と記しています。神武天皇はご存じ、第一
代天皇とされている天皇で、在位76年、『日本
書紀』では127歳、『古事記』では137歳まで長
生きをした?となっている天皇です。
父は鵜葺草葺不合神(うがやふきあえずのみ
こと)で、祖父・祖母は彦火火出見尊(ヒコホホデ
ミノミコト・山幸彦)と、海神の娘である豊玉姫命と
いうことになるようです。もう神世の話ですが…
…。余談ながら、豊玉姫は目から涙が出た形の
姿をしているそうです。それはこの神が、ゴマで
目を突いたからだといいます。そのため、いまで
も山ろくの神原地区ではゴマを作物として栽培し
ないということです。
★【古名添山説】
もうひとつの(2:添山(そほり)の山名由来説
は、『日向国志』という古書の「祖母は蓋(けだ)し
添(そほり)の古名を伝へ」との記述の「添山」か
らきているらしいのです。これは『日本書紀』(神
代下(かみのよのしものまき)・第九段)(巻第二)
天孫降臨の項に、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が
「稜威(いつ)の道別(ちわき)に道別(ちわ)き
て、日向(ひむか)の襲(そ)の高千穂峰(たかち
ほのたけ)に天降(あまくだ)ります」とあります。
その「一書」(5番目)には「降到(あまくだ)りま
しし処(ところ)をば、呼(い)ひて日向(ひむか・
宮崎県)の襲(そ)の高千穂の添山峰(そほりの
やまのたけ)と曰(い)ふ」とあるのです。この高千
穂の添山峰が、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が高
天原から降臨した高千穂峰だというのです。
この「添山説」についてはこんな伝承もありま
す。神武天皇が東征で豊後水道(関門海峡との
説も)で海戦となり、さらに台風が来て、神武の
船が転覆しそうになりました。この時、神武天皇
が、添利山(そふりやま)に向かって「彼の山は
日向の国、吾が祖母(豊玉姫)は海神、この難を
救いたまえ」と祈ったところ、荒海は鎮まり、無事
に目的を果たすことができたといいます。このた
め添利山を祖母山というようになったとしていま
す。また一説には「添利」が韓国語の「京」を意
味する「ソプル」によるともいわれてもいます。
★【山頂の二つの石祠】
さて、いま祖母山の山頂には古い石祠が二つ
まつられています。一つは、日向側の宮崎県高
千穂町五ヶ所に鎮座する祖母嶽神社の上宮で
す。もう一つは豊後側の神社で、大分県竹田市
の健男霜凝日子神社(たけおしもこりひこじんじ
ゃ)と、緒方町(大分県豊後大野市)の健男霜凝
日子麓社の上宮です。
日向側(宮崎県高千穂町)の「祖母嶽神社」
は、神武の父であるヒコホホデミとその母の豊玉
姫(とよたまひめ)などをまつっています。一方、
豊後側(大分県竹田市)の「健男霜凝日子神社」
(たけおしもこりひこじんじゃ)は、姥岳神である
豊玉姫(とよたまひめ)命ほかをまつっています
が、古くは神社名の神・健男霜凝日子神をまつ
っていたといいます。この神はその名のように、
昔は、霜などによる害を防ぐ自然神であったらし
い。緒方町(豊後側・大分県豊後大野市)の健
男霜凝日子麓社は、同神社の分霊なのだそうで
す。
★【支配権争い】
山頂のこの二つの石祠は、山上の支配をめぐ
って日向側(宮崎県)と豊後側(大分県)で争っ
たこともあったそうですから、「神さままつり」も人
間がからむとなんともおぞましいことになってしま
います。
★【緒方三郎惟栄伝説】
この山に関しては不可思議な話もあります。
昔、日向国(宮崎県)塩田というところにすむ塩
田太夫の娘の花本姫は大変美しく、両親は男が
近づけないよう別室に住まわせていました。姫が
18歳になった時、どこからともなく25歳くらいの
若者があらわれ、夜な夜な姫のもとへ通うように
なりました。
若者は、とてもこのあたりの者ともおもえないよ
うな、立て烏帽子に水色の狩衣(かりぎぬ)、貴
公子らしいりっぱな顔立ちに、姫も若者の求愛を
受け入れました。しかし間もなく侍女たちに気づ
かれ両親にも知られてしまいました。
姫はすでに身ごもっていましたが、相手がどこ
の誰だか分かりません。そこで両親は娘に針と
糸を渡し、若者の狩衣のすそに刺して、その糸
をたどって住まいを探すことにしました。塩田太
夫は、姫のほかに家来を4,50人も連れ、山や
谷を越えて日向と豊後の国境にある嫗岳(祖母
山)の山ろくの暗い洞穴の入り口に差しかっかっ
た時、中からうめき声が聞こえてきました。
太夫は花本姫に糸を引かせて合図を送り誰
なのかを確かめさせました。するとうめき声をあ
げていたのは大蛇でした。狩衣のすそに刺した
と思った針は、おとがい(あご)の下に刺さってい
ました。この大蛇こそ実は嫗岳大明神でありまし
た。大蛇は「自分はもうすぐ死ぬが、姫のお腹に
いるのは男児で、将来りっぱな武将になりその
一家は子孫の末まで繁栄するだろう」と言い残し
ました。
生まれた子供は顔かたちもりりしく、はだしで
野山を走るので、いつも足に「あかぎれ」が切れ
ているので、あかがり大弥太(大太童とも)呼ば
れました。その五代目こそこの地を治める、緒方
三郎惟栄(これよし、惟(維)義とも)であり、豊後
国緒方荘(いまの大分県豊後大野市緒方地区)
の領主だったのです。領主緒方三郎の体には
蛇の子孫の証しとして、蛇の尾の形とウロコがあ
りました。そのため、またの名を尾形三郎ともいっ
たということです。
この話は、『平家物語』(巻八・緒環(をだま
き))や、その異本だという『源平盛衰記』(古巻
第三十三)に、蛇と人間の娘(花御本姫の名で)
の神婚譚が記載されています。前者の『平家物
語』には、「豊後の国は、刑部卿(ぎょうぶきょう)
三位頼資卿の領地である。子息の頼経朝臣(あ
そん)を代官として置いていたが、都より豊後国
へ平家追討の命令が下り、
代官の頼経は、緒
方三郎維義(おがたのさぶろう これよし)にそ
の任を負わせた。この緒方三郎維義の先祖につ
いて伝承がある」と紹介しています。
★【竜駒伝説】
また祖母山頂には一本角の神馬伝説もありま
す。昔、祖母山は女人禁制で、緒方町側では女
性子供は黒岳山(池原)から上には登れません
でした。男性でも登山の際は、祖母北稜の屏風
岩で履き物類は脱ぎ捨て、それから上は素足で
お参りをするのがしきたりだったそうです。
そもそもこの山の頂には、角が一本生えた神
馬がすんでおり、これを「竜駒」と呼んでいまし
た。山頂南の奥祖母新道の下方、尾平急谷付
近にある岩屋は、竜駒の馬屋だといいます。この
場所はいまでも周辺をよく探せば馬の毛が落ち
ていて、拾って持ち帰ると幸運をつかめるといわ
れているそうです。
また東ろくの尾平地区から祖母山を望むと、
山頂は二つに分かれて見えます。北側のピーク
はお花畑になっていて、神馬竜駒はここの草地
でよく草を食(は)んでいたそうです。村人は、こ
のあたりのスズタケを家に持ち帰って、馬に食わ
せると病気にかかりにくくなるといっています。ま
た国見峠とお茶屋場(三県境)の頂との鞍部か
ら、ちょっと宮崎県に入り込んだところに湿地が
あり、「竜駒の池」という池もあります。人々はこれ
を「竜駒の水飲み場」といっているそうです。
ところで、祖母山西ろく熊本県側五ヶ所地区
の奧に、笈(おい)の町という小さな集落がありま
す。ここには「義経千本桜」に出てくる源義経の
重臣、佐藤忠信(道玄)にちなむ佐藤家があるそ
うです。この家にはこんな言いつたえがありま
す。昔、佐藤家に一頭のブチの馬(体に白斑の
ある)が飼われていました。
この馬のところに時々、祖母山頂にすむ神馬
「竜駒」が遊びに来て、広い山ろくの牧場で二頭
仲良く遊ぶ姿が見られたそうです。間もなくブチ
の馬との間に子馬が生まれました。生まれたの
はやはりブチで、その上頭に角が一本生えてい
たといいます。この馬は明治初年(1868)ころま
で生きていて、それを見た人もたくさんいたそう
です。いまその馬の角は高千穂町コミュニティー
センターに所蔵されているそうです。
★【登山史】
話は変わって昔から多くの著名人がこの山に
登ったそうです。江戸時代後期の医者、橘南谿
(たちばななんけい)がこの山に登ろうとしたの
は、天明2年(1782)の夏のこと。まだこのころは
「ウバガタケ」といっていたらしく、その紀行『西遊
記』に、「姥が嶽は豊後の国竹田の城下南四里
にあり。山の色黒く、雑樹生い茂り、抜群に秀で
て大なる山なり」と書いています。
しかし南谿は祖母山には登れなかったらし
い。天明2年は九州地方が大凶荒の年で、山は
荒れておりおまけに山賊などが出るといい、案内
人が見つからず断念したそうです。明治維新が
近づいて尊皇思想が高まった江戸末期あたりか
ら「ウバガタケ」は、「祖母山」の名で呼ばれるよう
になります。
幕末の天保8年(1837)になり、探検家松浦
武四郎という人が祖母山に登頂します。西国地
方旅行記の『西海雑誌』で、「……漸(ようやく)
にして絶頂にたどり付(つく)に……いさゝかひら
きたる木の間に板葺社壇あり。日向(宮崎県)国
祖母嶽三僧坊と誌せる額をかけたる神前に礼拝
して、其他の様子を考るに実に神寂たる霊山に
て、数千年斧斤を入れざる神山なれバ幾抱へと
もしれざる大木枝を交て葉をかさね」とあり、「祖
母嶽」の文字が見えます。
当時は、「祖母嶽の様子、道の善悪など尋問
ふに主人驚きたる面色にて、祖母嶽は是より頂
上まで五十里ありて、掌を立てる如く道甚だ険し
く、冬は雲封じ夏は毒虫多く魔所なりと恐れて、
土人といへども春秋の祭日の外は絶えて登山い
たす者なし……」などといわれていたそうです
(同『西海雑誌』)。
そんな時代に、松浦武四郎は地元の村人に
無理に案内を頼み、「峻(けわし)き山を直立に
上り行なれば出張たる岩の角は胸をさゝへて登り
がたきを、木の根に取つき足を運び千辛万苦し
て千辛万苦して頂上を極め」と同書に書いてい
ます。これを見るとかなり強引な人だったようで
す。
明治になると、英国人宣教師ウォルター・ウェ
ストンが来日して、富士山の次ぎにこの山に登り
ます(1890年11月)。いよいよ近代登山の幕開
けでありました。その記念碑が、五ヶ所高原の小
高い展望台「三秀台」に建つ鐘の塔として残って
います。
▼祖母山【データ】
★【所在地】
・宮崎県高千穂町と大分県豊後大野市(旧緒
方町)、竹田市にまたがる。JR本線豊肥本線
豊後竹田駅の南南東17キロ。JR緒方駅から豊
後大野市営バスで尾平高山、さらに歩いて5時
間で祖母山山頂。1等三角点(1756.39m)、
健男霜凝日子社(たけおしもこりひこしゃ)と祖母
嶽神社(そぼたけじんじゃ)上宮の石祠がある。
★【位置】国土地理院「電子国土ポータルWe
bシステム」から
・祖母山一等三角点:北緯32度49分41秒.
2728、東経131度20分49秒.3647
・祖母山四等三角点:北緯32度49分43秒.
9926、東経131度19分21秒.4081
★【地図】
・2万5千分1地形図名:「祖母山」
▼【参考文献】
・『角川日本地名大辞典44・大分県』竹内理三
(角川書店)1991年(平成3)
・『角川日本地名大辞典45・宮崎県』(角川書
店)1991年(平成3)
・『源平盛衰記』日本文学大系第16巻(国民図
書)1927年(昭和2)
・「週刊・日本百名山・48」(朝日新聞出版)
2008年(平成20)
・『新日本山岳誌』日本山岳会(ナカニシヤ出
版)2005年(平成17)
・『日本山岳ルーツ大辞典』村石利夫(竹書房)
1997年(平成9)
・『日本三百名山』毎日新聞社編(毎日新聞社)
1997年(平成9)
・『日本山名事典』徳久球雄ほか(三省堂)2004
年(平成16)
・『日本書紀(一)』(岩波文庫)校注・坂本太郎ほ
か(岩波書店)1995年(平成7)
・『日本伝説大系13』(北九州・福岡、大分、佐
賀、長崎県)荒木博之ほか(みずうみ書房)
(1987年(昭和62)
・『日本伝説大系14』(南九州・宮崎、熊本、鹿
児島)荒木博之ほか(みずうみ書房)1983年(昭
和58)
・『日本の民話20』(福岡・大分編)加来宣幸ほ
か(未来社)1974年(昭和49)
・『日本歴史地名大系45・大分県の地名』(平凡
社)1995年(平成7)
・『日本歴史地名大系46・宮崎県』(平凡社)
1997年(平成9)
・『平家物語』(日本文学全集7)「保元物語、平
治物語、平家物語」井伏鱒二訳(河出書房新
社)1960年(昭和35)
・『名山の文化史』高橋千劔破(河出書房新社)
2007年(平成19)
・このシリーズを、CDにまと
めました。【こちら】から。
…………………………………………
ちょっと【広告】です。スイマセン
★作者の本をどうぞ(アマゾンから)
【とよだ時】(旧とよた時)コーナーです。
https://www.amazon.co.jp/stores/author/B004L1SDTE
…………………………
★グッズあります。SUZURI社で販売しています。
https://suzuri.jp/toki-suzuri
…………………………………………
ちょっと【広告】です。スイマセン
★作者の本をどうぞ(アマゾンから)
【とよだ時】(旧とよた時)コーナーです。
https://www.amazon.co.jp/stores/author/B004L1SDTE
…………………………
★グッズあります。SUZURI社で販売しています。
https://suzuri.jp/toki-suzuri
…………………………
★下記はCD本です。(作者から発送します)。
山の妖怪神仏に出会う山旅。
・00『百名山の伝承と神話』(新)
・01『新・丹沢山ものがたり』
・02『全国の山・天狗ばなし』
・03『改訂・山の神々いらすと紀行』
・04『改訂・ふるさとの神々事典』
・05 ↓こちらもどうぞ(紙書籍版品切れ)
「電子書籍」または「中古書籍」をどうぞ。
▼山と渓谷社刊『日本百霊山』(電子書籍)
神仏、精霊、天狗や怪異と出会う山旅。山の愉
快な話。神話伝説姉妹版
<アマゾン>で。 <楽天ブックス>で。
………………
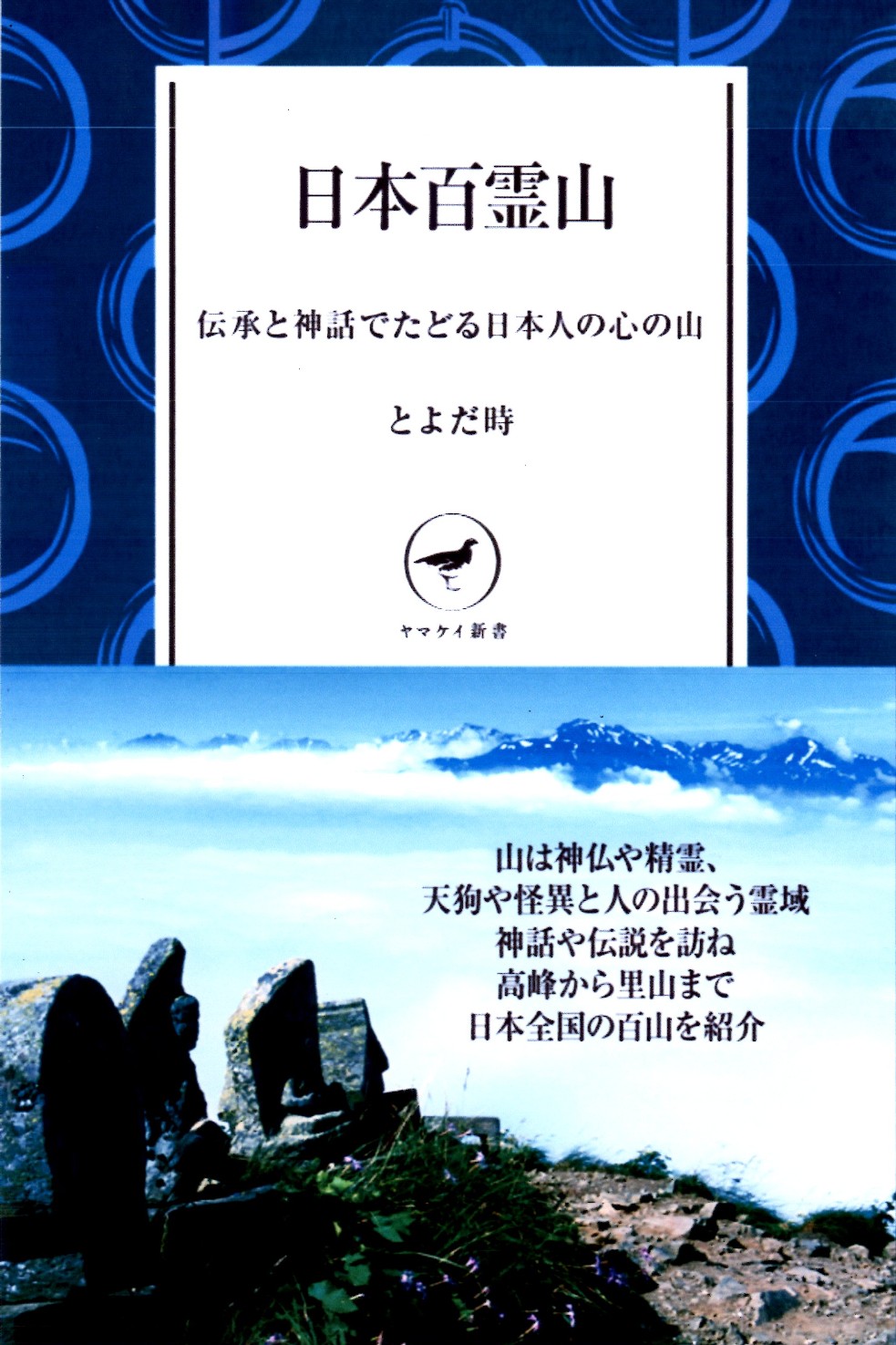
★その他CD本。
https://toki.moo.jp/cd-mihon/cd-mihon.html
▼SNSやっています
★Facebook:
https://www.facebook.com/tokitemg
★X(旧ツイッター):
https://x.com/tokitemg
……………………
【とよだ
時】山と田園の民俗伝承探査・漫画家
from
20/10/2000



|