山旅通信【ひとり画ッ展】
『日本百名山』の伝説と神話
(山の神・伝説神話)
【本文のページ】(04)
……………………………………
▼日本百名山94番「石鎚山」
「鍬(くわ)の雪形と役行者」
(長文です。ご興味ある部分を拾い読みしてくだ
さい)
★【目次】
・石鎚神社
・歴史・開山
・雪形
・伊曽乃神社創建伝説
・天皇の子に生まれ変わる・1
・天皇に生まれ変わる・2
・役行者の石鎚山探し
・ぬいぐるみの猿
・天狗伝説
・石鎚山データ
・参考文献
▼【本文】
★【石鎚山とは】
四国愛媛県にある石鎚山(いしづちさん)は、
石鎚山は彌山(みせん・1974m)、天狗岳(1982
m)、南尖峰(なんせんぽう)の三つのピークがあ
り、最も高い天狗岳の高さを石鎚山の標高にし
ています。これは西日本のなかでも最も高い山
になっています。
この山は切り立った矢じりの先のような天狗岳
や、その先の南尖峰、また夜明け峠から東方を
望めばそそり立つ御塔石(天柱石)の奇岩、さら
に穴の薬師の岩窟などがあり、なんとも険しい山
です。ここはその昔、弘法大師も修行した信仰の
山で、江戸時代から石鎚講がつくられ、信者た
ちは「ナンマイダンボー」(南無阿弥陀仏)と唱え
ながら登ったといいます。
★【石鎚山の山名】
この山は、石鎚山・石土山・石鉄山・石槌(マ
マ)山、石鉄山とも書き、「いしづちさん」「いしづ
ちやま」ともいうそうです。山名の由来は、頂上の
岩峰の形を「石鎚」と見たてたものといわれ、一
説に「ツ」は「之」の意味で、「チ」は霊力をもつ神
やものにつく接尾辞古代語「霊・チ」で、石之霊
(いしづち)だといいます。
★【展望】
山頂からは、眼下に西条市や周桑平野・瀬戸
内海を望み、遠く中国の伯耆大山・九州の久住
山、さらに太平洋まで望見できる。
★【石鎚神社】
石鎚山の神社は、弥山山頂にある「石鎚神社
頂上社」と、その北東中腹の成就というところに
ある「石鎚神社成就社」(口ノ宮社)、それに北ろ
く西条市西田(JR予讃線石鎚山駅近く)にある
「石鎚本社」の三社の通称です。古くは石鎚(石
鉄)山社ともいったそうです。
まつられている神は『古事記』にみえる石土毘
古命(いわつちひこのみこと)で、智・仁・勇の神
徳(しんとく)にちなんで山体の神像をまつりま
す。この神は、『古事記』(上つ巻)に、(伊耶那
岐・伊耶那美の2神が)「すでに神を生み竟(を)
へて、さらに神を生みたまひき。かれ、生みたま
へる神の名は、大事忍男(おほことおしを)の神。
次ぎに石土毘古(いはつちびこ)の神を生み、次
に、天之吹男(あめのふきを)の神を生み……」
とでてくる神。この神は岩や土をあらわす男神だ
といいます。
★【歴史・開山】
そもそもこの山は奈良時代に寂仙(じゃくせ
ん)という修行僧が修行をしたといわれていま
す。その寂仙が籠もるより以前に石鎚山頂にす
でに石鎚神が鎮座していたともいわれ、その時
代に役小角(えんのおづぬ)が、この神を石土蔵
王権現をまつって修験の山とあおがれました。ま
た役小角の法脈(定義)をひく「芳元」という人
が、石摺峰(石鎚山?)に、熊野権現を勧請した
という言いつたえもあったりします。
しかし急峻なこの山は、ふつう人には登れる
山ではありませんでした。その後、役ノ行者の亜
流とされる石仙道人が苦労して登山道を開き、
登山者のため中腹に成就社(じょうじゅしゃ)を建
立したといいます。成就社とは、もとは常住舎と
いい、山に籠もるための宿坊だったらしいとのこ
と。
中世以後は、神仏習合修験の山として本尊を
石鎚蔵王権現といったそうです。ただ『伊予温故
録(いよおんころく)』という本に「……役行者の
開きたるは瓶ヶ森(かめがもり)の方なり」とあり、
古くは石鎚山の東北東にある瓶ヶ森を石土山
(石鎚山)と呼び、石土神社もここにあったもの
を、中世いまの場所に遷座したとの記述もあるら
しい。
しかし、いずれにしても石鎚山は役行者に関
わる山に違いありません。平安時代末期に編ま
れた歌謡集『梁塵秘抄』(りょうじんひしょう)という
本にも、「聖(役行者)の住所は何処何処ぞ、大
峰葛城石の槌」と詠われているほどなのだそうで
す。その後、成就社を創立した石仙行者のあと
に上仙、光正などの大行者が次々とあらわれ、
山中に横峰寺や、前神寺などを創建していきま
した。
いま横峰寺は、真言宗御室派として西条市小
松町にあり、また前神寺は、真言宗石?派総本
山として西条市洲之内にあります。両方とも山号
は石?山(せきふさん)で、石鎚登山ロープウエ
イ山頂成就駅近くには奧前神寺もあります。明
治のはじめの神仏分離令で、修験道への締め
付けはあったようですが、いまでも神仏混淆の思
想は残っています。その証拠に、石鎚山への参
詣者は「ナンマイダンボー」(南無阿弥陀仏)と唱
え、石鎚の神を権現さまと呼んでいます。
この山も長い間女人禁制の時代がつづきまし
た。いま解禁になったとはいえ、毎年7月1日か
ら10日までは夏の大祭で、お山市と称されその
期間の内、1〜2日は女性の登拝が禁止されて
います。
★【雪形】
温かい愛媛県にある石鎚山にも雪形がでて、
山ろくの村人はその雪形を見て稲の籾種をまく
習慣があったそうです。愛媛県の東予地方の旧
周桑郡(丹原町、東予市)には、「石づちの雪鍬
(くわ)の柄と見ゆる頃、苗代時と知れよ三四郎」
という諺があるそうです(『山の紋章・雪形』)。こ
の雪形は「鍬形」とか「鎌形」と呼ばれています。
この雪形が出るのは、石鎚神社頂上社から北
へ下った面河分岐から西ノ冠岳方面、石鎚三角
点峰の先の尾根の中間点の北面の「雪ダルダ
ニ」(雪瀑谷)で、北ろくの老の川地区で加茂川
の本流に合流する谷のあたりです。道前地方(ど
うぜん・愛媛県
東予地方の旧周桑郡丹原町、
東予市)からは、平仮名の「く」の字に見えるそう
ですが、見る地点によっては変わってくるとのこ
と。また旧千足山村(いまの西条市)では、この
雪の形が「犬の伏せたるほど」に変わると、粟を
まくというそうです。
石鎚山には上述の「鍬雪」とは別に、「ミノカサ
雪」という雪形があらわれるといいます。これはや
はり石鎚山北ろく西条市の中村地区、土居地
区、谷ノ内地区の限られた里人に伝承されてい
る雪形です。これが出るのは「雪タルダニ」という
谷の標高900m位の低いところで、上記地区以
外では見ることができないといいます。これはミノ
カサを逆さにしたような形で、それがあらわれると
村人は焼畑に粟やヒエを蒔きました。
さらにこれは雪形ではないですが、愛媛県温
泉郡中島町睦月(いまの松山市)の人は、石鎚
山のことを「伊予太郎」といい、「伊予太郎が出た
ら(見えたら)明日は晴天」だとか。石鎚山が澄
み渡って望める日は「明日も晴れ」と決まってい
たのだそうです。
★【伊曽乃神社創建伝説】
この山には不思議な話がいくつかあります。
石鎚山の北ろく・西条市中野甲というところに伊
曽乃(いその)神社があります。この神社の神は
女神で、石鎚の神の妻だったそうです。ある時、
石鎚の神が山に登ろうとしましたが、この山は女
人禁制で、妻の伊曽乃の神は登ることができま
せん。
女神がウロウロとしていた時、すでに山頂の登
っていた石鎚の神が大石を投げました。石はガ
ラガラ、ゴロゴロと転がり落ちていき、やがて止ま
りました。石鎚の神は妻の伊曽乃の神に、大石
が止まったところに住むようにいいました。そのた
め、伊曽乃の神は石の止まった場所に神社(伊
曽乃神社)を建てて暮らすようになりました。そこ
からは石鎚山がよく見え、また夫の石鎚の神が
投げたという大石も神社の前にあるそうです。
★【天皇の子に生まれ変わる・1】
また、平安初期の弘仁年間(810〜824)に編
纂された『日本霊異記』(にほんりょういき)という
本に「……又、伊与国神野郡(いよのくにかみの
のこほり)の郷に山有り。名をば石槌山(いはづ
ちやま)と号(い)ふ。是(こ)れ即(すなは)ち、彼
(そ)の山に有(いま)す石槌(いはづち・槌は木
偏)の神のみ名なり。其(そ)の山高く?(さが)し
くして、凡夫(ただびと)は登り至ること得ず。但
(ただ)し浄行の人のみ、登り至りて、居住(とど
ま)れり」という一文があります。
……要するに、伊予の国神野郡に石槌山(マ
マ)という山があった。これはその山におわす石
槌の神の名である。その山は高く険しく、心身を
清めて修行するものだけが登り住めた。孝謙天
皇の時代、この山に寂仙という僧が籠もって修行
し、菩薩とあがめられていた。
ところで天平宝字(てんぴょうほうじ)2年(758・
奈良時代)、寂仙は臨終の時、文書を書き記し、
弟子に与えて「わたしは28年後、国王の子に生
まれ変わり、名前を神野と名づけられるだろう」と
告げた。
それから28年後、延暦5年(786年)に、桓武
(かんむ)天皇の皇子に生まれ、その名を神野親
王(のちの嵯峨天皇)と名づけられたと書かれて
いるのです。要するに僧の寂仙が生まれ変わっ
て嵯峨天皇になったのだそうです。
★【天皇に生まれ変わる・2】
さらに元慶(がんぎょう)3年(879年・平安前
期)の民間の巷談、俗説、訛言、古老の伝誦(し
ょう)、怪異などを採録した『文徳実録』(もんとく
じつろく・日本文徳天皇実録の略)(菅原是善・
都良香ら)にも同じような話が載っています。「伊
予国神野郡。昔有高僧名灼然。称為聖人。有弟
子名上仙。住止山頂。精進練行。過於灼然。諸
鬼神等(くさかんむりの外字を使用)。皆随(した
がう)?指(いし)。上仙甞(嘗の異体字)従容語
所親檀越云。我本在人間。有同天子之尊……」
と漢字ばかりがならんでいます。
……つまりの話が以下のようになるようです。
「昔、伊予国の神野郡に灼然(しゃくねん)という
偉い坊さんがいた。弟子に上仙(『日本霊異記』
の寂仙のことか?)という行者がいて石鎚の山上
に住み、精進練行の結果、灼然行者を超えて山
の鬼神たちを自由に使役できるようになった。
(中略)その上仙が亡くなる際、自分が天皇に生
まれ変わるであろうと予言した」。
「また、この上仙行者に深く帰依していた橘姫
が、来世は上仙とともに過ごしたいといいながら
亡くなった。神野天皇とその后橘夫人は、ふたり
の生まれ変わりである。親王の名は、乳母が伊
予国神野郡の出身で「神野」と呼ばれた女性で
あったことに由来しているといい、以後、郡名を
親王名をはばかって、新居(にい)郡と改めた」と
いうのです。両方の話とも、天皇の子に生まれ変
わることを予言したというのです。不思議な話と
いうか、不思議な本が残っているものです。以上
は『文徳実録』(もんとくじつろく・日本文徳天皇
実録の略)という書物にある話です。
★【役行者の石鎚山探し】
かつては、石鎚山脈の一つ瓶ヶ森(かめがも
り)は、石鎚山より古くから開けていて、その頂上
には寺も建っていたという言いつたえがありま
す。またその瓶ヶ森が遠くへ飛んでいってその
跡にいまの石鎚山ができたなどの話もあります。
その中のひとつの話です。ある時役行者が石
鎚山を探しに出かけましたが、なかなか見つかり
ません。その途中で、一人の老人がハツリ(斧)
を研いでいるのに出会いました。役行者が「何を
しているのか」と聞くと、老人は「このハツリを研い
で細くして針にするのだ」といいます。行者は「ず
いぶん気の長い話だ」と思いましたが、やはり何
事も辛抱が大事なのだと再び石鎚山を探しに出
かけました。
そこで「オトウ」という地名のところの岩穴の奧
で修行をしていると、近くの大きな石が割れまし
た。そこから2町(200mあまり)ほど登ってみると、
「穴の薬師」の洞窟の中に、石鎚山が大蛇にな
ってこもっていました。そこで役行者が「そこでは
人々が参詣に来ようと思っても来られない」とい
いました。それを聞いた石鎚山は空へ舞い上が
り、いまの場所におさまったといいます(『山岳宗
教史研究叢書12』)。
★【ぬいぐるみの猿】
石鎚山ろく地方の住民は、ぬいぐるみの猿を
山上にもっていく風習があるそうです。それを杖
の先にくくりつけ、もって帰り神棚にまつっておき
ます。子供がはしかにかかったり病気をした時
は、このぬいぐるみの猿を拝めばよく治るのだと
いいます。この地方では猿は山の神の使いだと
考えられているそうです。
★【天狗伝説】
さて、石鎚山にも天狗がいることになっていま
す。それについて「石鎚山勤行式」というものに
は、「南無眷属(けんぞく)宝(法)起坊、大天狗、
小天狗、十二八天狗、有摩那(うまな)天狗、数
万騎天狗にに至るまでうんぬん」とあります。この
ように石鎚山の天狗岳には大天狗、法起坊(ほう
きぼう)と眷属の小天狗たちがウジャウジャいるこ
とになっています。それをとりまとめるのが法起
坊大天狗だといいます。
ところでここを開山した役ノ行者は、江戸時代
後期の寛政11年(1799年)に、天皇から神変大
菩薩(しんぺんだいぼさつ)というおくり名を貰う
までは、法起菩薩とか法起大菩薩と呼ばれてい
ました。法起とは役ノ行者の法号だったのです。
そんなことから石鎚山法起坊は、役ノ行者の化
身ではないかとか、先述の石仙聖人、上仙道人
などだという説もあります。
しかし、天狗研究家は石仙、上仙が生きた時
代が嘉祥3年〜天安2年(850〜858年)であるこ
とや、『伊予温故録』や「前神寺縁起」、その他文
献を考察の結果、いくら法起坊天狗が法名を継
いでいるからといって、役ノ行者などこの山の開
拓者の化身とは考えられず、結局は大昔から天
狗岳に生まれていた地主神を後の世に祭り上げ
たものだろうとしています。
▼石鎚山【データ】
★【所在地】
・愛媛県西条市と面河村との境。予讃線伊予小
松駅の南15キロ。JR予讃線伊予西条駅からバ
ス、1時間10分石鎚ロープウエイ前停留所下車、
ロープウエイで山頂成就下車。さらに歩いて3時
間20分で弥山(1972m)。石鎚神社と石鎚神社
頂上山荘がある。さらに20分で天狗岳(1982
m)。
★【位置】国土地理院「電子国土ポータルWebシ
ステム」から検索
・弥山:北緯33度46分08.63秒、東経133度06分4
9.05秒
・天狗岳:北緯33度46分03.96秒、東経133度06
分54.3秒
★【地図】
・2万5千分の1地形図「石鎚山(高知)」
▼【参考文献】
・『神々の系図』川口謙二(東京美術)1981年(昭
和56)
・『角川日本地名大辞典38・愛媛県』(角川書店)
1981年(昭和56)
・『古事記』:新潮日本古典集成・27『古事記』校
注・西宮一民(新潮社版)2005年(平成17)
・『山岳宗教史研究叢書12』「大山・石鎚と西国
修験道」宮家準編(名著出版)1979年(昭和54)
・『山岳宗教史研究叢書18』「修験道史料集(2)
西日本篇」五来重編(名著出版)1984年(昭和5
9)
・『修験道の本』(学研)1993年(平成5)
・『神社辞典』白井永治ほか編(東京堂出版)198
6年(昭和61)
・『新日本山岳誌』日本山岳会(ナカニシヤ出
版)2005年(平成17)
・『図聚天狗列伝・西日本』知切光歳著(三樹書
房)1977年(昭和52)
・『天狗の研究』知切光歳(大陸書房)1975年(昭
和50)
・『日本山岳風土記8・中国四国九州の山々』
(宝文館)1960年(昭和35)
・『日本山岳ルーツ大辞典』村石利夫(竹書房)1
997年(平成9)
・『日本三百名山』毎日新聞社編(毎日新聞社)1
997年(平成9)
・『日本山名事典』徳久球雄ほか(三省堂)2004
年(平成4)
・『日本登山史・新稿』山崎安治著(白水社)1986
年(昭和61)
・『日本霊異記』(にほんりょういき)薬師寺の僧景
戒著:平安初期の仏教説話集。平安初期822年
(弘仁13)ごろ成立。:日本古典文学全集・第6
巻「日本霊異記」中田祝夫校注・訳(小学館)199
3年(平成5)
・『文徳実録』(もんとくじつろく・日本文徳天皇実
録の略)。文徳天皇一代の民間の巷談、俗説、
訛言、古老の伝誦(しょう)、怪異などを採録:『国
史大系3』国史大系編修会(吉川弘文館)1966
年(昭和41)所収
・『名山の日本史』高橋千劔破(ちはや)(河出書
房新社)2004年(平成16)
・『山の紋章・雪形』田淵行男著(学習研究社)19
81年(昭和56)
・このシリーズを、CDにまとめました。【こちら】から。
…………………………………………
ちょっと【広告】です。スイマセン
★作者の本をどうぞ(アマゾンから)
【とよだ時】(旧とよた時)コーナーです。
https://www.amazon.co.jp/stores/author/B004L1SDTE
…………………………
★グッズあります。SUZURI社で販売しています。
https://suzuri.jp/toki-suzuri
…………………………………………
ちょっと【広告】です。スイマセン
★作者の本をどうぞ(アマゾンから)
【とよだ時】(旧とよた時)コーナーです。
https://www.amazon.co.jp/stores/author/B004L1SDTE
…………………………
★グッズあります。SUZURI社で販売しています。
https://suzuri.jp/toki-suzuri
…………………………
★下記はCD本です。(作者から発送します)。
山の妖怪神仏に出会う山旅。
・00『百名山の伝承と神話』(新)
・01『新・丹沢山ものがたり』
・02『全国の山・天狗ばなし』
・03『改訂・山の神々いらすと紀行』
・04『改訂・ふるさとの神々事典』
・05 ↓こちらもどうぞ(紙書籍版品切れ)
「電子書籍」または「中古書籍」をどうぞ。
▼山と渓谷社刊『日本百霊山』(電子書籍)
神仏、精霊、天狗や怪異と出会う山旅。山の愉
快な話。神話伝説姉妹版
<アマゾン>で。 <楽天ブックス>で。
………………
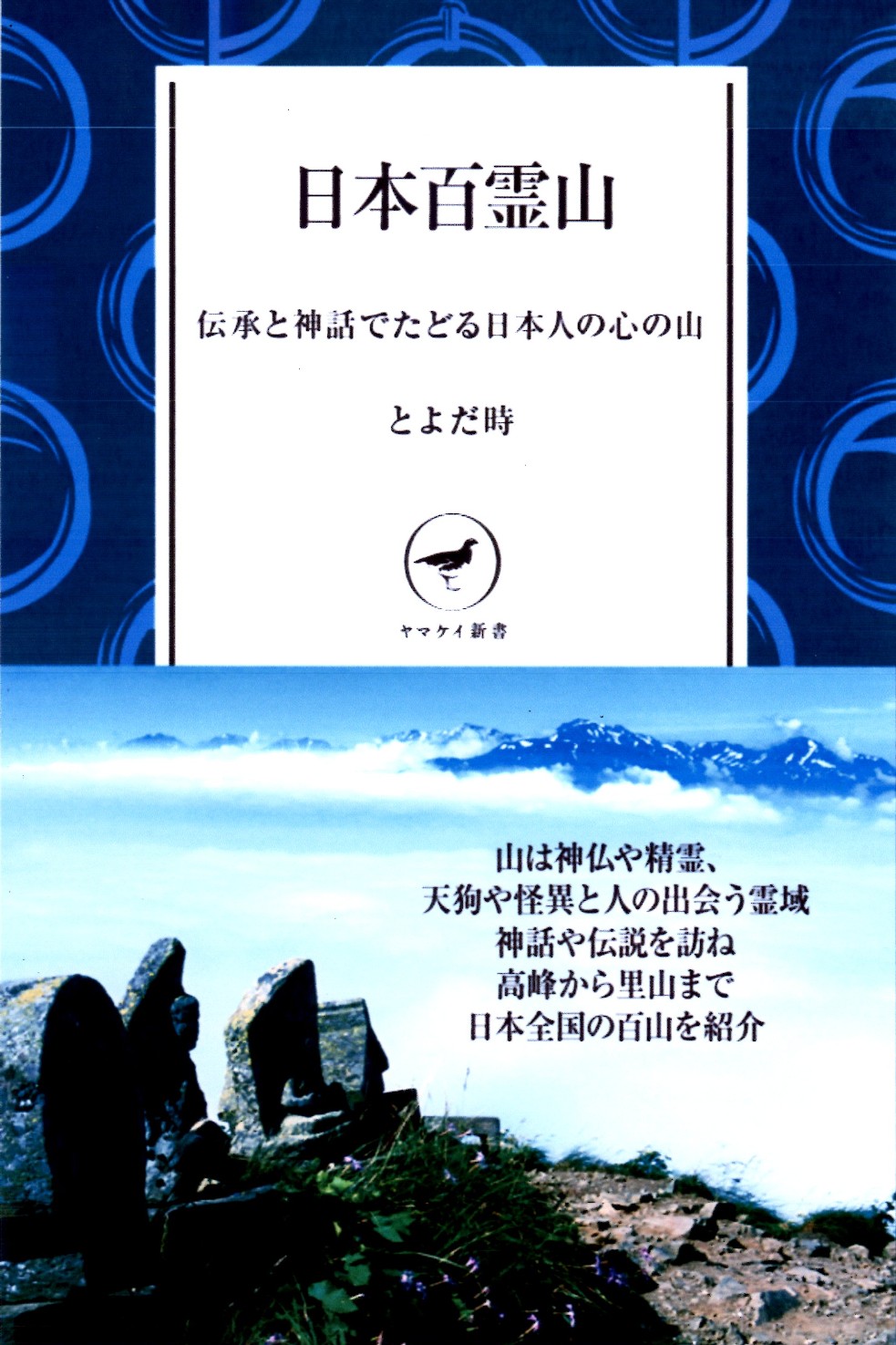
★その他CD本。
https://toki.moo.jp/cd-mihon/cd-mihon.html
▼SNSやっています
★Facebook:
https://www.facebook.com/tokitemg
★X(旧ツイッター):
https://x.com/tokitemg
……………………
【とよだ
時】山と田園の民俗伝承探査・漫画家
from
20/10/2000



|