『伝承と神話の百名山』
本文のページ(02)
【とよだ時】(豊田時男)
……………………………………
▼12:八幡平「山名と秋田県側の伝説」
【説明略文】
八幡平の名は、坂上田村麻呂が蝦夷との戦い
で勝利し、八幡神社を勧請したとの説。また
八幡太郎義家がここに登ったことに由来する
との説。さらにここは湿地で、地面が柔らか
く、柔(ヤワ)と所を意味する(タ)、それ
に、山上の湿原の意味「タイ」を合せたとい
う説などがあるそうです。
・岩手県八幡平市と、秋田県鹿角市、仙北市と
の境。
【本文】は下段にあります。長いです。
【本文】
岩手県と秋田県にまたがる八幡平(はちま
んたい)は、名前のように平らで、明るく開
けた草原状山塊。その地名の由来はいくつか
あるようです。
まず坂上田村麻呂説。平安時代初期、坂上
田村麻呂が蝦夷(えみし・伝説では岩手山の
鬼・大猛丸)との戦いで、敵将を討ち取った
ことを神に感謝、また敵将大猛丸の供養を弔
(とむら)って八つの旗(すなわち八幡)を
立てて八幡神社を勧請(かんじょう)したと
の説。
また平安時代後期、源氏の八幡太郎義家が、
安倍一族との戦いの時にここに登ったことに
由来するとの説。さらにここは湿地で、地面
が柔らかい所のため、柔(ヤワ)と所を意味
する(タ)、それに、山上の湿原の意味「タ
イ」を合せたという説です。
ところで、ここ八幡平は奥羽山脈に連なる
大火山高原です。こんなところですから、温
泉があちこちにあり、岩手県側には藤七(と
うしち)・草ノ湯・安比(あっぴ)などの温
泉が、秋田県側には熊沢川やその支流域に蒸
ノ湯(ふけのゆ)、大深(おおぶか)、後生掛
(ごしょがけ)、大沼などの温泉があります。
八幡平アスピーテラインを、八幡平山頂を
越えて秋田県鹿角市に入ると「ふけの湯温泉」
があります。「ふけの湯」は、子宝の湯とし
て有名で、こどもが授からない女性が、浴衣
一枚でムシロの上に寝て、下からの蒸気で身
を蒸(ふ)かす温泉。湯槽には木製の金精さ
まがたくさんあったところ。子宝の湯にふさ
わしく、ここには金精さまのお祭りもありま
す。
毎年6月10日金精大明神の祭典には、ほら
貝を吹く烏帽子姿の人を先頭に、猿田彦神、
神主、そのあとには、金精さまを抱いた女性
がつづきます。金精さまは全身を白布につつ
まれ、ふたりの女性に一体ずつ抱かれて、山
中の「ふけ湯神社」に向かって行列をつくっ
て登っていきます。
ふけの湯神社に着くと、金精大明神に祝詞
をあげ、金精さまの白布をとって奉納します。
あとはお神酒、お菓子が配られて式が終了。
その後、出発した湯治場前の広場に帰り、仮
装行列やのど自慢を楽しむということです。
さぞかしご利益がありそうです。
この山も伝説がたくさんあります。その1
【オナメ・モトメ伝説】:オナメとは愛人の
ことで、モトメとは本妻のことだといいます。
八幡平アスピーテラインを、頂上のバス停を
越えて鹿角市に入るとあらわれる温泉のなか
に、後生掛(ごしょがけ)温泉があります。
ここに伝わる「オナメ・モトメ伝説」です。
この温泉の地獄谷には、熱湯と蒸気がすさま
じい噴出口がふたつ、競い合うようにしてな
らんであります。江戸時代中期のこと、いま
の岩手県雫石から、秋田県の生保内(おぼな
い)方面に荷物を運ぶ、喜平という牛方(う
しかた)がいました。
ある時喜平は、仙岩峠(せんがんとうげ・
雫石町と秋田県仙北市・標高895m)に差し
かかった時、追いはぎに襲われました。深い
傷を負った喜平は、後生掛の湯までたどりつ
き、ここで養生することになりました。ある
日ひとりの巡礼娘が、ここにたどり着きまし
た。親の供養で恐山や仏ヶ浦を回まわって帰
りでした。ちょうど喜平が、露天風呂で全身
傷だらけの体を休めているところいるところ
でした。
あまりの痛ましさに放っておけず、看病や
世話をするようになりました。そのお陰か喜
平に元気が戻り、ふたりは夫婦になり喜平は
夏は牛方、冬はマタギをして幸せに暮らして
いました。
ところが喜平には故郷の岩手の雫石(久慈
とも)に妻がいたのです。妻は帰らない夫を
心配しながら探し歩き、人づてに後生掛の温
泉いることを知り訪ねてきました。しかしそ
こには仲睦まじく暮らしているふたりの姿が
あったのです。
雫石から来た妻は、夫がすでに娘に心を移
していることを知ると、大いに悲しんで、近
くの熱湯噴出する大湯沼(※後生掛温泉の南
側にある)に飛び込んでしまいました。一方、
何も知らなかった娘も、人の夫を奪った罪の
深さを悔いて、あとを追うように身を投げて
しまいました。
その時突然ドーンと、大音響とともに新た
にふたつの噴泉が出現しました。それ以来、
ふたつの噴泉は、競い合うように「ゴボー、
ゴボー、ゴー」という不気味な音を立てて、
熱湯を噴出し続けています。喜平も自分の罪
の深さにおののき、二人の女の後生を弔いつ
づけたということです。そんなことから、ふ
たつの大噴泉を「オナメ、モトメ」と名づけ、
地名を「後生掛」というようになったという
ことです。
その2【だんぶり長者】:昔、出羽国(北
秋田郡)独鈷(とっこ)村(いまの大館市比
内町独鈷)に、気だての優しい美しい娘が住
んでいました。ある夜夢に老婆が現れ、「汝
の夫になるべき男はこの川(いまの米代川)
の上流の小豆沢という所にいる。そこへ訪ね
て行き結婚せよ」という。娘は川上の小豆沢
村(いまの鹿角市八幡平小豆沢)に行き結婚、
仲睦まじく住んでいました。
ある年の元旦、夢にふたたび老婆が現れて
「われは大日神霊なり。汝さらに川上に行き
て住むならば有徳の人となるべし。われはこ
の地に鎮座して人民を守護するなり」とのお
告げを受けました。素直な夫婦は、お告げ通
りこの場所に土壇をつくって大日神をまつ
り、自分たちは米代川の上流の田山村(いま
の岩手県安代町田山)の奧の平間田という所
に移り、田畑を耕して仲良く暮らしていまし
た。
ある日、野良仕事で疲れた男がウツラウツ
ラしていたとき、岩かげからトンボ(方言で
はだんぶり)が男の鼻に2,3度尾を触れま
した。目をさました男は、「夢のなかで、い
ままで飲んだこともない甘い酒を飲んだ」と
話したのです。
男はトンボが、自分が寝ている間に、不思
議なことをしたことを聞き、トンボが飛んで
いった方へ行ってみると、泉がわき出ていて
トンボがたくさん飛んでいます。ちょっと飲
んでみると、まさしく夢の中で飲んだ酒だっ
たのです。夫婦は神さまからがお授けになっ
たものだと喜び、この水を村の人たちにも分
け与えました。
すると病人はたちまち治り、寿命が延びる
というありさま。この評判が広まり、大勢の
人がここに引っ越してきました。それからは、
その人たちの米のとぎ汁で川が真っ白にな
り、「米白川」の名がつきました。これがい
まの「米代川」だそうです。その後夫婦はど
んどん長者になっていきました。
長者には秀子という評判の美しい娘がおり
ました。このうわさは遠く京の継体天皇(け
いたい・第26代とされる天皇。在位507〜
531)の耳に入り、娘は吉祥姫と名を変え帝
の妃になりました。夫婦は「長者」の称号を
与えられ、トンボ(だんぶり)のお陰で長者
になったので「だんぶり長者」と呼ばれ、幸
せに暮らしたということです。
ただ、不思議なこの泉の水は、長者や夫婦
が亡くなると普通の水に変わってしまい、い
まはその旧跡だけが残っています(「旅と伝
説」第十二巻三号)。(※類話多し)。
▼八幡平【データ】
【所在地】
・岩手県八幡平市と秋田県鹿角市と仙北市田
沢湖(旧仙北郡田沢湖町)との境。いわて銀
河鉄道大更駅の西22キロ。JR東北新幹線盛
岡駅からバスで八幡平終点。二等三角点(161
3.3m)がある。
【地図】
・2万5千分の1地形図「八幡平(秋田)」
▼【参考文献】
・『角川日本地名大辞典5・秋田県』新野直
吉ほか編(角川書店)1980年(昭和55)
・『角川日本地名大辞典3・岩手県』高橋富
雄ほか編(角川書店)1985年(昭和60)
・「旅と伝説」三元社編(三元社)1939年(昭
和14):「民俗学資料集成」第十二巻三号(岩
崎美術社)
・『日本山名事典」徳久球雄ほか(三省堂)2
004年(平成16)
・『日本山岳ルーツ大辞典」村石利夫(竹書
房)1997年(平成9)
・『日本伝説大系2・中奥羽編』(岩手・秋田
・宮城)野村純一編(みずうみ書房)1985
年(昭和60)
・『日本歴史地名大系3・岩手県の地名』森
嘉兵衛(平凡社)1990年(平成2)
・『日本歴史地名大系5・秋田県の地名』今
村義孝ほか(平凡社)1980年(昭和55)
・『名山の民俗史』高橋千劔破(河出書房新
社)2009年(平成21)
▼こんな話をCDにまとめてあります。
【山のCD本・見本】
……………………………………
【広告】ご希望の方にお譲りしています
▼【おもしろ山と田園の本・見本】
・01『新・丹沢山ものがたり』
・02『伝承と神話の百名山』
・03『全国の山・天狗ばなし』
・04『山の神々いらすと紀行』
・05『続・山の神々いらすと紀行』
・06『ふるさとの神々何でも事典』
・07『続・ふるさとの神々事典』
・08『家庭行事なんでも事典』
・09『健康野菜と果物』
・10『ひとの一生なんでも事典』
・11『ふるさと祭事記(歳時記)』
・12『野の本・山の本』
…………………………
▼山と渓谷社刊『日本百霊山』(紙書籍・電子書籍)
神仏、精霊、天狗や怪異と出会う山旅。山の知識を
もう一つアップ。
★ヤマケイ『日本百霊山』ホームページ
https://www.yamakei.co.jp/products/2816120561.html
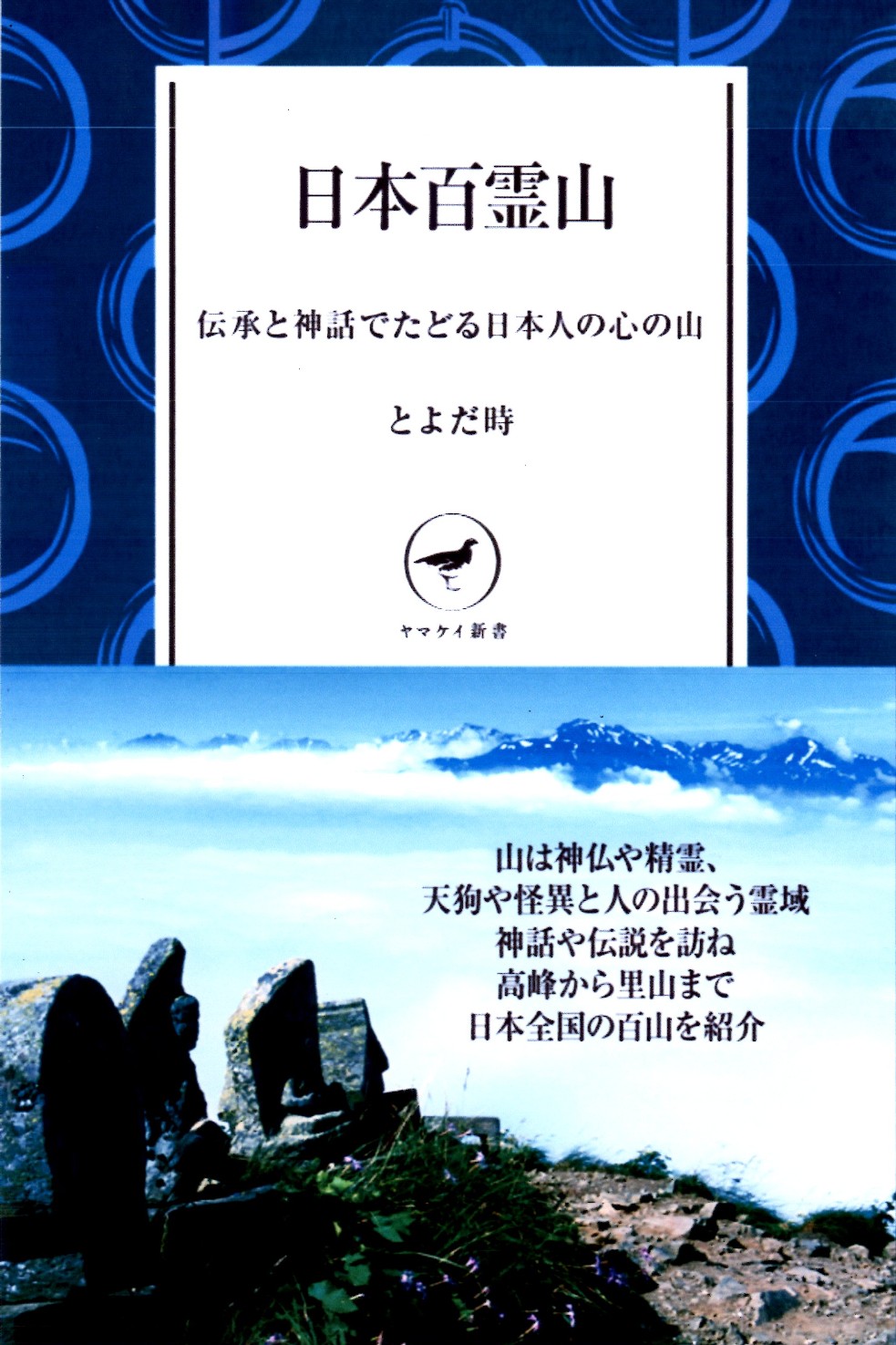
山の伝説伝承神話が満載の本
……………………………………
【TOP】ページ「峠と花と地蔵さんと……」へ
………………………………………………………………
|